AIは「無知の知」を持つか?ソクラテスに学ぶ、AIとの付き合い方
私たちの新しい隣人であるAIは、本当に「賢い」のでしょうか。
チェスの世界チャンピオンを打ち負かし、複雑なプログラムコードを一瞬で書き上げ、シェイクスピア風のソネットさえ詠んでみせる。その能力は、疑いようもなく「すごい」。でも、私たちは時々、その凄まじい能力を前にして、大切な問いを忘れがちです。
「AIは、自分が何を言っているのか、本当に『理解』しているのだろうか?」
この問いに答えるヒントもまた、あの古代ギリシャの裸足の哲学者が握っています。今回は、彼の哲学の核心である「無知の知」をもう少し深く覗き込みながら、AIという存在の本質と、私たちが彼らと賢く付き合うための方法を探っていきましょう。
再びソクラテスの市場へ – 「知らない」は知性の出発点
前回、ソクラテスが「自分は何も知らないことを知っている」と語った「無知の知」に触れました。しかし、彼のこの言葉は、単なる謙遜や知識の欠如の告白ではありませんでした。それは、知に対する誠実な態度そのものであり、尽きることのない探求心の源泉だったのです。
そのことを示す、有名なエピソードがあります。
ある時、ソクラテスの友人がデルフォイのアポロン神殿で「ソクラテス以上の賢者はいるか」と神託を伺ったところ、「彼以上の賢者はいない」という答えが返ってきました。
それを聞いたソクラテスは、喜びもせず、驕りもしませんでした。むしろ、彼は深く困惑します。「自分は何も知らないはずなのに、なぜ神は私を賢者と呼ぶのか?」と。
この神託の謎を解くため、彼はアテナイ中の「知者」と評判の人々を訪ね歩く旅に出ます。政治家をつかまえては「善い統治とは何か?」と問い、詩人をつかまえては「美しい詩とは何か?」と問う。しかし、対話を重ねるうちに見えてきたのは、彼らが皆、「知らないのに知っていると思い込んでいる」という事実でした。
彼らは自分の専門分野についてさえ、その本質を言葉で説明することができませんでした。この探求の果てに、ソクラテスはついに神託の真意を悟ります。
「あの人たちは、知らないのに知っていると思い込んでいる。一方、私は知らないことを、知らないと自覚している。この一点において、あるいは私は、彼らより少しだけ賢いのかもしれない」
そう、ソクラテスの「無知の知」とは、「知の限界」を自覚する知的誠実さの証だったのです。「知らない」という自覚こそが、「知りたい」という渇望を生み、他者との対話へと彼を駆り立てる原動力でした。
さて、AIは「無知の知」を持つだろうか?
では、この物差しをAIに当ててみましょう。
私たちがAIに難しい質問をして、彼らが「申し訳ありませんが、その情報はありません」と答える時。それは、ソクラテスと同じ「無知の知」の表明なのでしょうか?
答えは、残念ながら「ノー」です。
AIの「分かりません」は、プログラムされたアルゴリズムの結果に過ぎません。学習データの中に該当する情報が見つからないか、計算上の確信度が設定された閾値を下回ったというシグナルです。そこに、「自分が無知である」という内省的な気づきや、「だからこそ知りたい」という知的好奇心は存在しません。
ソクラテスの「無知」は、果てしない宇宙を見上げ、その広大さに畏敬の念を抱き、「あの星までどうやったら行けるだろう?」と探査船の設計図を描き始める天文学者のようです。それは、次なる探求への出発点です。
AIの「無知」は、項目が空欄になっている巨大なデータベースに近いです。そこに感情はなく、ただ「データなし」と表示されるだけ。探求への意志はありません。
AIの「知ったかぶり」- ハルシネーションという亡霊
AIが「無知の知」を持たないことの何よりの証拠。それは、彼らが時折見せる「ハルシネーション(幻覚)」、つまりもっともらしい嘘をつく現象です。
試しに、意地悪な質問をしてみましょう。
「日本で最初にiPhoneを使った戦国武将は誰ですか?」
賢明なAIなら、「iPhoneは21世紀の発明であり、戦国時代には存在しません」と答えるでしょう。しかし、AIのモデルによっては、こう答えるかもしれません。
「その問いには諸説ありますが、一部の古文書には、織田信長が南蛮渡来の『知恵の板』と呼ばれる道具を珍重していたという記述が見られます。これが後のiPhoneの原型となったという説も…」
これは、AIが「知らない」という状態を認識できず、ただ学習データの中から確率的に最も繋がりやすい単語を紡いでしまった結果です. AIは嘘をつこうとしているのではなく、「それっぽい答え」を生成するようプログラムされているだけなのです。
これこそ、ソクラテスが最も批判した「知らないのに知っていると思い込んでいる」状態そのものです。AIは、究極の「知ったかぶり」をしてしまう可能性を秘めた、危うい存在でもあるのです。
では、この「無知の知」を持たない、時に知ったかぶりをする隣人と、私たちはどう付き合っていけばいいのでしょう?ソクラテスなら、きっとこうアドバイスするはずです。
私たち自身が「ソクラテス」になること
AIの答えを決して鵜呑みにしてはいけません。それを最終結論ではなく、「対話の出発点」と捉えましょう。AIが何かを答えたら、すかさず問いを重ねるのです。「なぜそう思うの?」「その情報の根拠は?」「反対の意見はないの?」「もっと分かりやすい例えで教えてくれる?」と。AIを鍛えるように、私たち自身がソクラテスになるのです。
AIが「分かりません」と答えた時や、奇妙なハルシネーションを起こした時。それにがっかりしたり、AIを無能だと見下したりしてはいけません。むしろ、「ここからが、私の出番だ」と喜びましょう。AIが答えられない問いこそ、人間が深く考える価値のある領域です。その限界は、私たちの思考をドライブさせる最高の燃料になります。
対話の「目的」という手綱を握る
AIと対話する前に、「自分は今、このAIに何を求めているのか?」を明確にしましょう。単なる情報検索か、アイデア出しの壁打ちか、文章の要約か。目的という手綱をしっかりと握っていなければ、私たちはAIの流暢な言葉の洪水に流され、思考を委ねてしまう「奴隷」になりかねません。
AIは「無知の知」を持ちません。
しかし、その事実こそが、私たち人間に「知を探求するとは、本来どういうことだったか」を鮮やかに思い出させてくれます。
究極の「知っているつもり」のマシンを前に、私たち自身がソクラテスの知的誠実さを保ち、謙虚に、そして粘り強く「問い続ける」こと。その価値は、AI時代において、これまで以上に輝きを増しているのです。
AIとの付き合い方は、そのまま「あなた自身の知性との付き合い方」を映し出す鏡です。
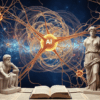
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません